田んぼの準備が忙しくなる頃、ほっと一息。ご近所や、町内会などで集まって、竹の子狩りのイベントを催します。
新井の竹の子は・・
竹の子というと、あの、春に出回るゴロッとした焦げ茶色したものを思い浮かべる人がたくさんいることでしょう。
事実新井でもその「孟宗竹」の竹やぶもよく見かけますし、スーパーにならんだものを買って食べたりもします。
ところが、新井でふつう竹の子というと、今回紹介するもののことをさして、太いものと区別するために「姫竹の子」とか、「ネマガリタケ」と言ったりしますが、正確な名前は「チシマザサ」といいます。
 特徴は、見た通り「細い」ということと、孟宗竹の竹の子に比べて、えぐみが少なく歯触りの感触がさくさくしていることです。さらに孟宗竹のように、根際を掘る感じではなく、先端部分を折りとるようにしてとるので、かさもなく、一度の料理で数十本と必要になり皮をむく手間もかなりのものです。さらに、孟宗竹より早く鮮度が失われますので、採ったその日中には加工してしまわなければいけません。それだけに「採れたてで作る竹の子汁」は、季節に一度は食べたいごちそうなんです。
特徴は、見た通り「細い」ということと、孟宗竹の竹の子に比べて、えぐみが少なく歯触りの感触がさくさくしていることです。さらに孟宗竹のように、根際を掘る感じではなく、先端部分を折りとるようにしてとるので、かさもなく、一度の料理で数十本と必要になり皮をむく手間もかなりのものです。さらに、孟宗竹より早く鮮度が失われますので、採ったその日中には加工してしまわなければいけません。それだけに「採れたてで作る竹の子汁」は、季節に一度は食べたいごちそうなんです。


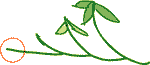 採るには
採るには
↑写真をごらんください。右半分が竹やぶで、今後左に向かって広がって行きます。この竹の子の特徴は、地面を這うように株を広げていくので、新芽(竹の子)が地面と水平に出ることで、ネマガリタケのゆえんです。その後斜めに伸び上がり、葉を広げて親株となります。
そのため出始めのころは、これから伸びようとしている方向の先端に、手のひらを広げたように出てきます。
竹の子採りにもいろいろあって、写真のような場所は採りやすい場所ですが、プロが、太くて節の詰まった質のいい竹の子を採る場合などは、知らない人にとっては簡単に入れないような奥地へ、ヘルメットをかぶり(竹で頭を傷つけないように)、ラジオを持って(熊よけや、場所の頼りに)、時には二人でペアになって採りにいくそうです。
たのしい竹の子狩り
竹の子狩りは、秋のきのこ狩りとならんで、季節の待ちどおしいイベントの一つです。「今度の週末は竹の子狩りね」と、ご近所でさそいあわせたり、町内会の行事として、みんなで出かけて楽しみます。通常山菜の場合は、採ってきてからあく抜きなどの処理があったり、それ自体がメインのおかずになりにくいために、全体の料理の一部として食べる場合が多いのですが、竹の子は違います。
朝からみんなで出かけて、昼には収穫した竹の子を汁にして、持っていったおにぎりといっしょに食べます。大人はちょいと一杯(のつもりで・・)。
昔は、山でわき水をくんで、焚き火をして作ったそうですが、今は、手軽にキャンプ場(高床山キャンプ場や斐太の県民休養地など)といった炊事施設のあるところを利用しています。当日は先発隊が早めにいって竹の子を採っておいたり、別の山で採ってきたりして準備しておくことが多くなりました。
「純正。新井のたけのこ汁」
お料理としては、たけのこ汁は一番の人気メニューです。その他にも、皮付きのまま網で焼いたり、たけのこご飯、玉子とじ、煮付け、炊き合わせなどにできますが、いずれのお料理にもこの竹の子の味はピカイチです。
処理の特徴は、孟宗竹は皮ごとゆでますが、この竹の子の場合は皮をむいてからゆでるところが違います。
たけのこ汁は、もともとは竹の子狩りイベントの昼食ですから、気どらない素朴な味付けが一番似合います。従って作り方なんてありません。材料全部をまとめて水で煮てやれば出来上がりです。竹の子、豚バラ肉、サバ缶、玉葱、じゃがいも、味噌、酒粕といったところです。(「豚肉はいれない」とか、「じゃがいもはいれない」とか、そこらへんはいろいろありますが・・。)煮上がったら、最後に溶き卵で仕上げます。
昔の味噌(自分の家で作った)は、煮るほどに甘みがでて、今のような塩辛いような感じがなかったそうです。つまり、だしも使わずに「竹の子そのものの旨みをたんのうできた」といいます。
朝、みんなで収穫した採りたての竹の子を、山の清水と昔ながらの味噌で汁をつくってわいわい食べる。これが「純正新井のたけのこ汁」なんだろうなぁ。
今度みんなでやろ〜よ。
お楽しみいただきました、「あらいの山菜」は今回をもって終了いたします。この後、続編も構想中です。ご意見ご希望などありましたら、お気軽にメールをおまちしています。(あらいの山菜編集担当;村越)